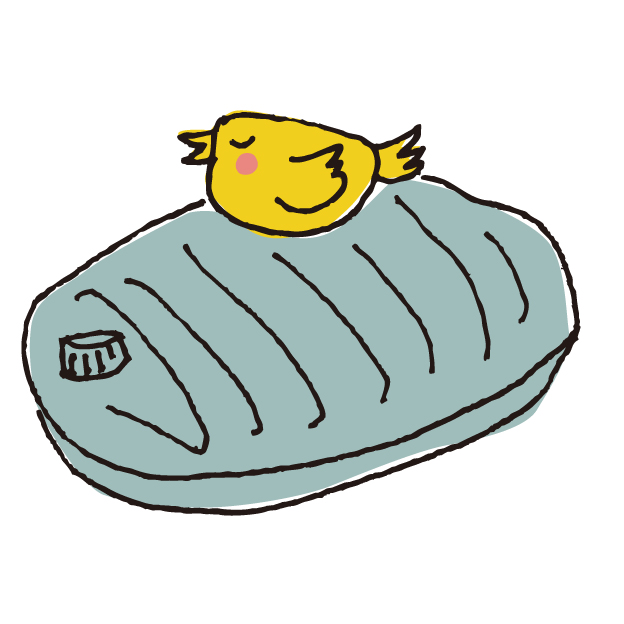月経不順(生理不順)
成熟した女性の体では、約1か月の周期で排卵や、子宮内膜の変化が起こります。排卵後、妊娠に至らなかった場合は、子宮内膜が剥離し血液などとともに排出される“月経”が起こります。月経は25日~38日の周期で起こるのが通常です。月経周期がこの範囲よりも短くなったり長くなったりする状態が“月経不順”で、一般に“生理不順”とも呼ばれます。
月経不順には、周期が通常より短くなる“頻発月経”と、長くなる“希発月経”があります。また、妊娠していないのに3か月以上月経がない状態を“無月経(続発性無月経)”と呼びます。月経不順の原因には、ストレスや過度の体重減少のほか、卵巣や子宮の病気、ホルモンを調節する脳部位の病気、薬剤の影響などがあります。ストレスなどが原因で一時的に月経周期が乱れることは少なくありません。一方で、ホルモンが乱れ長期的に排卵異常が続くと不妊につながることがあり、腫瘍など治療が必要な病気が隠れている場合もあります。月経不順の原因は多岐にわたるため、月経周期の乱れが続くなど気になる症状がある場合は、産婦人科で相談するとよいでしょう。月経不順の原因には、ホルモンバランスの乱れや卵巣の病気などがあります。ストレス、過度な減量、環境の変化などはもっともよく見られる原因の1つです。自然に改善する場合もありますが、月経不順にはさまざまな原因が考えられるため、異常を感じた場合は自己判断せず、専門医を受診するとよいでしょう。ダイエットや肥満、ストレス、疲労、環境の変化などがホルモンバランスに影響し、短期的に月経が乱れることは珍しくありません。過度な体重減少や過度なストレスはホルモンを調節する“視床下部”という脳部位に影響し、卵巣機能の障害を引き起こすことがあります。多嚢胞性卵巣症候群は、月経不順の原因として比較的多い病気です。成熟した女性の5~8%に発症するといわれていますが、この病気自体の原因は分かっていません。男性ホルモンの量が増えることにより排卵しにくくなり月経不順や無月経を引き起こすとされています。そのほか、卵巣の腫瘍や、早発卵巣不全(40歳未満で閉経のような症状が起こる病気)などで卵巣機能が低下すると、月経不順になることがあります。脳下垂体は、月経に関わるホルモンを調節するはたらきをしています。脳下垂体に腫瘍ができたり、その腫瘍を手術で取ったりしたことによって、ホルモンのバランスが変わると月経に影響が出ます。また、甲状腺機能の機能が低下した影響でプロラクチンというホルモンが増えることがあり、排卵を障害し月経不順となることもあります。うつ病やパニック障害の治療のために処方される精神安定剤の影響で、プロラクチンが高まり、排卵が止まることがあります。また、抗がん剤治療や放射線治療、卵巣の手術の影響で、卵巣機能が低下して排卵が障害され月経不順となることがあります。月経が止まる原因として妊娠や閉経がありますが、これらは自然な変化であり病気ではありません。また、初めての月経から数年間は排卵周期が定まらないことも多く、月経不順があっても正常の乱れの範囲内といえる場合もあります。一方、月経不順だと思っていたものが、実は月経ではなく不正出血(月経以外の性器出血)である場合があります。不正出血では、ポリープや子宮の腫瘍、血液凝固異常などほかの病気が隠れている場合がありますので、心当たりがある場合は病院で診察を受けるのがよいでしょう。月経不順では、月経周期が24日以内と通常より短くなる“頻発月経”、39日以上と長くなる“希発月経”、妊娠していないのに3か月以上月経が来ない“無月経(続発性無月経)”、といった症状が見られます。月経不順にともなって、排卵周期の乱れがあったり、排卵が止まっていたりする場合もあります。また、1回の月経の継続日数が普段より長く、あるいは短くなったり、不正出血が見られたりすることがあります。頻繁な不正出血は量が多いときには貧血を引き起こすこともあります。また、ホルモンバランスの乱れによって、骨の量が減少したり、子宮体がんになる確率が高くなったりすることがあるといわれています。長期にわたり卵巣機能の低下が続くと、不妊の原因となることがあります。多嚢胞性卵巣症候群の場合は、無月経や月経不順のほか、男性ホルモンの影響で体毛が濃い、にきびができやすい、太りやすく痩せにくい、といった症状が現れます。また、プロラクチンというホルモンの値が異常に高い状態(高プロラクチン血症)では、妊娠していなくても月経が止まり、少量の母乳が分泌される場合があります。
月経が遅れている場合には、まず、妊娠でないことを確認します。診断のためには、問診のほか、血中ホルモン濃度の検査や、超音波、CT、MRIなどを用いた画像診断などが行われます。必要に応じて、子宮の細胞や組織を取って検査したり、染色体検査が実施されたりすることもあります。問診では、月経の状態、既往歴、妊娠分娩歴、体重の増減、ストレス、内服薬、家族の既往歴、月経不順以外の症状の有無などについて確認します。栄養状態や骨量の検査が行われることもあります。基礎体温は排卵の有無を確認するために有効なので、基礎体温をつけている場合は問診の際に伝えるとよいでしょう。視診や経腟超音波検査では子宮や卵巣の状態を確認します。細胞の状態を確認したほうがよいと判断された場合は、子宮の細胞や組織を採取して検査することがあります。ホルモンバランスの乱れについては、原因となる部位(視床下部、脳下垂体、卵巣など)と、乱れのパターンを見極めるために、複数のホルモンについて血中濃度を測定します。また、検査のためにいくつかのホルモンを投与し、反応としての出血の状態を確認することがあります。月経不順では、その原因と、妊娠を希望しているかどうかで治療が異なります。初経から間もない、あるいは閉経が近いと月経不順が起こりやすい状態であるため、ひどい貧血などが見られない場合には経過観察となることもあります。原疾患として脳や卵巣などに腫瘍が見つかった場合は、薬物治療または手術による切除を試みることもあります。甲状腺機能低下症に対しては、甲状腺ホルモンを補充することによって排卵が正常に回復することが期待されます。また、服用中の薬剤が原因で高プロラクチン血症となっている場合は、治療中の病気との優先度を考えながら薬の減量や処方の変更を検討し、必要に応じてプロラクチンを下げる薬を使用します。体重減少が原因である場合は、運動の制限や食事内容の調整によって適切な体重を目指します。体重やストレスのコントロールのために心理的なサポートが必要なときには、カウンセリングが行われたり、専門医へ紹介されたりすることがあります。低用量ピルにはホルモンのバランスを整える効果が期待され、症状に応じて処方されることがあります。エストロゲンというホルモンが長期に不足している場合は骨量が減少する危険があるため、ホルモン補充に加えて、カルシウムやビタミンD3が処方されることがあります。妊娠の希望がある場合には、排卵誘発剤が使用されます。
漢方と鍼灸
黄体ホルモン、卵胞ホルモン、女性ホルモン全般、子宮、卵巣、乳首、自律神経、癌などの異常反応が出ている反応穴から最適な漢方、食養生やサプリ、ツボを選択して改善していきます。
煎じ
・当帰芍薬散(当帰・川芎・芍薬・白朮・茯苓・沢瀉)『金匱要略』
浮腫みがあり、血行が悪く、冷え性な女性に用いられます。
・桂枝茯苓丸(桂枝・茯苓・牡丹皮・桃仁・芍薬)『金匱要略』
お血を減らしていきます。
ボタンピには駆瘀血作用があり内出血や腫瘤を除き、さらに抗炎症作用があります。桂枝は血行を良くして瘀血作用を助け、茯苓は利尿作用、芍薬は鎮痙作用があります。
・温経湯(呉茱萸・当帰・川芎・芍薬・人参・桂枝・阿膠・生姜・牡丹皮・甘草・半夏・麦門冬)『金匱要略』
・加味帰脾湯(人参・白朮・茯苓・黄耆・竜眼肉・酸棗仁・遠志・木香・甘草・当帰・生姜・大棗・柴胡・山梔子)『内科摘要』
・帰脾湯(白朮・茯苓・黄耆・竜眼肉・酸棗仁・人参・木香・甘草・生姜・大棗・当帰・遠志)『厳氏済生方』
・牛膝散(牛膝・桂枝・芍薬・桃仁・延胡索・当帰・牡丹皮・木香)『婦人大全良方』
・四物湯(地黄・芍薬・当帰・川芎)『太平恵民和剤局方』
・折衝飲(芍薬・桃仁・桂枝・紅花・当帰・川芎・牛膝・牡丹皮・延胡索)『産論』
・桃核承気湯(桃仁・大黄・甘草・芒硝・桂枝)『傷寒論』
・当帰四逆加呉茱萸生姜湯(当帰・芍薬・甘草・木通・桂枝・細辛・生姜・呉茱萸・大棗)『傷寒論』
・芎帰補血湯(当帰・川芎・白朮・茯苓・熟地黄・陳皮・烏薬・香附子・乾姜・益母草・牡丹皮・甘草・生姜・大棗)『万病回春』
・逍遥散(甘草・芍薬・当帰・茯苓・白朮・柴胡・生姜・薄荷葉)『太平恵民和剤局方』
・逍遥散(当帰・芍薬・柴胡・黄芩・川芎・熟地黄・半夏・人参・麦門冬・甘草・生姜)『寿世保元』
・下瘀血丸(大黄・桃仁・䗪虫)『金匱要略』
・紅花当帰湯(当帰・川芎・芍薬・熟地黄・香附子・枳殻・延胡索・厚朴・茴香・柴胡・陳皮・三稜・莪朮・牛膝・紅花・甘草・生姜)『寿世保元』
・通経湯(当帰・川芎・芍薬・地黄・大黄・桂皮・厚朴・枳殻・枳実・黄芩・蘇木・紅花・烏梅・生姜・大棗)『万病回春』
・抵当丸(水蛭・虻蟲・桃仁・大黄)『傷寒論』
・八物湯(当帰・川芎・芍薬・熟地黄・人参・甘草・茯苓・白朮・生姜・大棗)『瑞竹堂経験方』
・八珍湯(当帰・川芎・芍薬・熟地黄・人参・白朮・茯苓・甘草・生姜・大棗)『薛立齋』
・馬明湯(鬱金・紅花・大黄・甘草・石膏・馬明退)『和田東郭』
・秘蔵益胃升陽湯(柴胡・升麻・甘草・当帰・陳皮・人参・神麴・黄耆・白朮・黄芩)『蘭室秘蔵』
・和血通経湯(当帰・三稜・莪朮・木香・熟地黄・桂皮・紅花・貫衆・蘇木・血竭)『衛生宝鑑』
など(薬局製剤以外も含む)
子宮下垂・子宮脱
子宮が本来の位置よりも下がる状態のうち、子宮の下降が軽度で腟の外に脱出しない状態をさします。子宮下降の状態が進むと、子宮脱の状態に移行します。また、子宮の下降が軽度でも、子宮周囲の膀胱、直腸、尿道、小腸などの臓器も一緒に下がってしまうことがあり、それぞれ膀胱瘤、直腸瘤、尿道脱、小腸脱と呼ばれます。これら骨盤内の臓器が本来の位置より下がってくる状態を総称して、骨盤臓器脱もしくは性器脱と呼びます。骨盤の底には、筋肉(骨盤底筋群)や、器官や組織をつなぐ靭帯組織(内骨盤筋膜)があり、これらが協調して骨盤内の臓器を支えています。子宮下垂は骨盤底の筋肉や結合組織などの骨盤支持構造が経腟分娩や骨盤内の外科手術などにより障害された状態や、加齢により支持構造自体が緩むことで生じます。長時間の立ち仕事、重いものを持ち上げる仕事、肥満や便秘など骨盤への負担が強い状態も要因となります。子宮下垂は、子宮の下降の程度が軽度で、自覚症状はほとんどないことが多いです。しかし、歩行時や重いものを持ったとき、トイレでしゃがんだとき、入浴時などに子宮が腟の入口近くまで下降することで、腟にものが挟まったような違和感(子宮下垂感や外陰部違和感)が生じる場合があります。またそのような状態で腟に指をいれるとピンポン大の硬い塊(子宮の入口部分)に触れます。膀胱や直腸が下がった場合には、膀胱の出口が圧迫されることで排尿困難、夜間の頻尿、尿意の切迫感などの症状、直腸の出口が圧迫されることで便意が頻回に生じる、排便が困難になるなどの症状が見られる場合があります。内診により容易に診断できます。さらに、腹圧を加えることで子宮が下がる状態を作り出し、子宮の下降の程度を評価します。必要に応じて、超音波、MRIやCT等の画像検査を行い、子宮や子宮と周囲との組織との関係を調べることがあります。
症状が現れていない場合は、経過観察の上で骨盤底筋体操を行うことが基本です。症状が現れている場合や、子宮周囲の臓器の骨盤臓器脱(膀胱瘤や直腸瘤など)がみられる場合には、程度に応じて保存的加療(ペッサリー)や手術療法を選択する場合があります。骨盤底筋体操では骨盤底の筋肉を鍛える運動により、軽度の尿漏れや子宮下垂を改善できる場合があります。具体的には、尿道、肛門、腟を締めて緩めるというトレーニングを、仰向け、四つん這い、座位などで行います。手術を望まない場合や手術適用となるほどの骨盤臓器脱を認めない場合には、腟内にペッサリーと呼ばれるドーナツ状のリングを挿入し、子宮や膀胱、直腸などの下降した臓器を押し上げ支えます。ペッサリーには硬質プラスチック製やシリコン製など素材があり、さまざまなサイズがあります。腟の広さや臓器の下降の状態は患者さんごとに異なるため、最適なリングのサイズもそれぞれに異なります。初回の挿入段階では、リングのサイズが合わないとリングが抜けたり、痛みを生じたりすることがあり、何度か最適なサイズを調整する必要があります。また、長期的に使用すると、リングが腟壁に当たることで発赤したり、感染により帯下(おりもの)が増加したりすることがあるため、子宮下垂の状態評価と合わせて定期的なリングの交換を行います。脱出している臓器の種類や程度に応じてさまざまな方法があり、施設や術者によっても多少のばらつきがみられます。障害を受け、緩んだ骨盤底の筋肉や結合組織などの骨盤支持構造を修復あるいは補強することが手術の基本です。手術は、腟から行う場合とお腹から行う場合、あるいはそれを組み合わせる場合があります。お腹からの手術は、侵襲の少ない腹腔鏡手術で行われることが増えています。膀胱の下降がみられる場合は腟の前壁の修復 (前腟壁形成)、直腸の下降がみられる場合には腟の後壁の修復 (後腟壁形成)や 肛門挙筋縫縮術が単独あるいは併用して行われます。近年は、ポリプロピレン素材のメッシュを腟の後方に入れ、丈夫な壁を作り補強する方法が行われています。子宮摘出の有無にかかわらず施行可能ですが、メッシュ特有の合併症(感染、疼痛、メッシュの脱出など)もあります。また、腹腔鏡下で行う腹腔鏡下仙骨膣固定術が保険適応となり、注目を集めています。こうした手術は、術後に再度骨盤支持構造が緩むことで再発するリスクがあります。再発予防のために肥満、便秘を防ぐ、骨盤周りの筋肉を鍛える (骨盤底筋体操)などを行うことが大切です。
漢方と鍼灸
筋や腱をしっかりさせる食養生、内臓下垂を改善する漢方や食養生、腹筋、背筋、内臓筋や骨盤底筋体操などを組み合わせて治療します。
・補中益気湯(黄耆・人参・白朮・甘草・当帰・陳皮・柴胡・升麻・生姜・大棗)『脾胃論』
黄耆・柴胡・升麻に筋肉の収縮力を正常にして。アトニー状態を改善する作用があります。
・黄耆建中湯(芍薬・黄耆・生姜・桂皮・大棗・甘草・膠飴)『金匱要略』
・調中益気湯(橘皮・黄柏・升麻・柴胡・人参・炙甘草・蒼朮・黄耆)『李東垣』
・提気散(黄耆・人参・白朮・当帰・芍薬・乾姜・柴胡・升麻・甘草・姜活)『寿世保元』
・医王湯(黄耆・甘草・人参・乙井・陳皮・升麻・柴胡・白朮・生姜・大棗)『脾胃論』
・下瘀血丸(大黄・桃仁・䗪虫)『金匱要略』
・参耆湯(人参・黄耆・当帰・地黄・白朮・芍薬・茯苓・升麻・桔梗・陳皮・甘草・生姜・大棗)『万病回春』
など(薬局製剤以外も含む)
子宮腺筋症
子宮内膜に似た組織が子宮の筋肉の中にできる病気を指します。子宮のほとんどは子宮筋層と呼ばれる筋肉でできていて、その内側は子宮内膜という粘膜組織で覆われ、子宮内膜は受精卵を育むベッドとしての役割を担っています。子宮内膜に関連する病気として子宮内膜症がよく知られていますが、子宮内膜症は子宮内膜あるいはそれに似た組織が子宮の外に発生する病気で、卵巣、卵管、ダグラス窩か、仙骨子宮靱帯、膀胱子宮窩などに好発します。また子宮内膜は子宮の外だけでなく、子宮を構成する子宮筋層内に生じることもあり、これを子宮腺筋症と呼びます。子宮腺筋症は、10歳代前半から閉経を迎えるまでの幅広い年齢で起こる可能性がありますが、40歳代の人に多く、特に出産を経験した人に多いといわれています。そのほか、子宮内膜の操作を伴う手術(掻爬手術・帝王切開・子宮筋腫の手術)を経験した人に多いという報告もあります。子宮腺筋症の原因はまだよく分かっていません。発生のメカニズムとしては、何らかの原因によって子宮内膜が子宮筋層内に潜り込んでしまうという説や、子宮内膜症と同じように発生するという説、もともと子宮筋層内にあった子宮内膜から発生する説があります。子宮腺筋症になってもまれに症状がないこともありますが、多くの場合で月経困難症(強い月経痛)や過多月経(経血量が多い)、不正出血、月経時以外の腹痛・腰痛などが現れます。不妊や流産、早産の原因になることもあります。月経困難症は月経に伴って子宮が大きくなることや、子宮筋層内での内膜組織の出血が原因で子宮の収縮が強くなるために起こると考えられ、月経過多や不正出血は子宮内膜の近くに発生することで起こります。子宮腺筋症では女性ホルモンの1つであるエストロゲンの影響を受けるため、閉経を迎えるまで進行し続け症状も強くなっていきますが、閉経を迎えると軽快します。まず内診で子宮の状態を確認し、子宮が大きくでこぼこがなく丸みを帯びているなどの所見がある場合に子宮腺筋症を疑い、次いで超音波検査やMRI検査が行われます。子宮腺筋症の治療には大きく薬物療法と手術があります。薬で治すことはできませんが、症状の改善が期待できるため、症状が強い場合にはまず薬物療法が行われます。薬物療法でも症状が改善せず、日常生活に大きな支障をきたしている場合に手術が検討されます。一般的にはまず症状に応じた薬が用いられ、月経困難症や月経過多に対して鎮痛剤や鎮けい剤、止血剤などが用いられます。このような薬を使っても効果が得られない場合などには、プロゲスチン製剤(内服薬)、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤(内服薬)、ダナゾール(内服薬)、GnRHアゴニスト(注射薬・点鼻薬)といったホルモン剤を使用し、女性ホルモンの分泌を抑えたり病巣に直接作用したりして症状の緩和を図ります。そのほか、黄体ホルモンを持続的に放出する器具を子宮内に留置する治療法(子宮内黄体ホルモン放出システム)が選択されることもあります。薬物療法で十分な効果がみられない場合に手術が検討されます。手術の方法として子宮腺筋症核出術、子宮内膜焼灼術、子宮摘出術などがあります。子宮腺筋症核出術は子宮腺筋症の病変部分だけを切除する方法で、子どもを産むことを希望する人に行われることがあります。ただし、有用性についてはまだ十分に分かっていません。子どもを産むことを希望しない人や閉経に近い人などには子宮内膜焼灼術や子宮全摘術が選択されます。子宮内膜焼灼術は主に子宮を残したい方を対象としたもので、マイクロ波を用いて子宮内膜や子宮筋層を壊死させます。子宮摘出術は、その名のとおり子宮を摘出する手術です。その方法として子宮全摘出術や子宮腟上部切断術がありますが、いずれにしても子宮腺筋症が存在する子宮そのものを取り除くため、これらの中では唯一の根治治療となります。
漢方と鍼灸
子宮内膜の組織が傷がついた箇所や出産で広がった筋肉層の中に入り込んで発症するもの。子宮の痛みの強い箇所から最適な漢方、食養生やサプリ、ツボを選択して治療にあたります。
通常のお血の漢方に工夫が必要です。
・当帰芍薬散(当帰・川芎・芍薬・白朮・茯苓・沢瀉)『金匱要略』
浮腫みがあり、血行が悪く、冷え性な女性に用いられます。
・桂枝茯苓丸(桂枝・茯苓・牡丹皮・桃仁・芍薬)『金匱要略』
お血を減らしていきます。
・温経湯(呉茱萸・当帰・川芎・芍薬・人参・桂枝・阿膠・生姜・牡丹皮・甘草・半夏・麦門冬)『金匱要略』
・加味帰脾湯(人参・白朮・茯苓・黄耆・竜眼肉・酸棗仁・遠志・木香・甘草・当帰・生姜・大棗・柴胡・山梔子)『内科摘要』
・芎帰調血飲(当帰・川芎・白朮・茯苓・熟地黄・陳皮・烏薬・香附子・乾姜・益母草・牡丹皮・甘草・生姜・大棗)『万病回春』
・柴胡疎肝湯(柴胡・橘皮・川芎・芍薬・枳殻・甘草・香附子・山梔子・生姜)『張氏医通』
・升陽燥湿湯(升麻・葛根・独活・姜活・芍薬・人参・炙甘草・柴胡・防風・甘草・大棗・生姜)『内外傷弁惑論』
・清玉散料(当帰・川芎・地黄・牡丹皮・陳皮・黄連・升麻・甘草・半夏・茯苓・芍薬・蒼朮・香附子・黄芩・柴胡・生姜)『寿世保元』
など(薬局製剤以外も含む)
子宮内膜症・チョコレート膿腫
子宮内膜症
本来なら子宮の内側の壁を覆っている子宮内膜が、子宮の内腔以外の部位(卵巣や腹膜、子宮の壁の中など)に発生し、発育を続ける病気です。20~30歳代の若い世代の女性に発症することが多いとされています。子宮内膜は本来、受精卵が着床する場所です。女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)のはたらきによって妊娠に向けて増殖・成熟が促されますが、排卵後2週間ほど経っても着床がない場合は、子宮内膜が子宮の壁から剥がれ落ちて出血と共に体外へ排出されます。このような現象を“月経(生理)”と呼び、月経が終了すると次の妊娠の機会に備えて再び子宮内膜の増殖が開始されます。この約1か月の性周期(月経)は、子宮内膜症で形成される異常な部位に生じた子宮内膜様組織にも影響を与え、月経前後に出血を生じて腹痛などを引き起こします。また、この異常な子宮内膜様組織は体外へ排出されずに体の中に留まり、炎症を起こし周囲の組織と癒着して慢性的な腹痛を引き起こしたり、不妊症の原因になったりすることも少なくありません。治療では薬物療法や手術などを行うものの、再発するリスクが高く将来的にがんになることもあるため、慎重な経過観察が必要となります。子宮内膜症は、本来なら子宮の内腔にしか存在しないはずの“子宮内膜組織”が子宮内腔以外の場所に発生し、増殖することによって発症します。どのようなメカニズムで子宮内膜症が発症するのか明確に分かっていない部分が多いものの、20~30歳代の若い女性に発症しやすいことなどから女性ホルモンの作用によって引き起こされると考えられています。また、経血がお腹の中に逆流する現象が発症に関わっている説もあり、初潮が早い・妊娠回数が少ない・性周期が短いなど、月経を経験する回数が多い人ほど子宮内膜症の発症率が高くなることが分かっています。子宮内膜症は子宮内腔以外の部位に子宮内膜が発生する病気で、特に卵巣や子宮、腸や膀胱の隙間、子宮を支える靱帯、卵管などに発症しやすいとされています。一方で、肝臓の周囲や肺など子宮と遠く離れた部位に発症するケースも珍しくありません。子宮内膜症を発症すると、早期の段階では月経中を中心に下腹部の痛みが強くなります。また、進行すると周囲の組織と癒着を引き起こし月経痛が悪化するだけでなく、慢性的な腰痛や下腹部痛、排便時や性交時の痛みなどが現れるようになります。まれではありますが、尿管や腸管の閉塞が起こることもあります。また、肺に発症した場合は、月経時に肺の一部に穴が開いて息苦しさや胸痛などを引き起こす“気胸”を伴うことが知られています。さらに、子宮内膜症は卵巣や卵管などに癒着を引き起こすため不妊症の原因となるケースも多く、子宮内膜症患者の約3割は不妊症であるとのデータもあります。子宮内膜症が疑われるときは次のような検査が必要となります。子宮の大きさや位置、周辺組織との癒着の有無などを調べるために画像検査が必要になります。第一に簡便に行える超音波検査を実施しますが、状態をさらに詳しく調べ、がんなど別の病気との鑑別を行うためにCTやMRIによる精密検査が行われることも少なくありません。子宮内膜症が子宮の筋層内に起こると経血量が増えるため、慢性的に貧血となることがあります。そのため、貧血の有無など全身の状態を確認するために血液検査を行うのが一般的です。また、子宮内膜が卵巣内で増殖することによって生じる“チョコート嚢胞”などの場合は、がんとの鑑別をするために腫瘍マーカー(がんを発症すると体内での産生が盛んになる物質)の数値を調べることがあります。ただし、これは子宮内膜症でも上がることも多く、“高値だからがん”と即断はできません。骨盤MRIとの結果も考慮し、総合的に判断することになります。画像検査や血液検査などでも子宮内膜症の診断を下すことは可能ですが、子宮から離れた部位に発生している子宮内膜症が疑われるときは、腹腔の中に内視鏡を挿入して病変の状態などを詳しく調べる検査が行われることがあります。体に負担がかかる検査ですが、正確な診断が可能です。そのまま手術に移行することも多くあります。子宮内膜症と診断された場合は、重症度や発症部位、将来的な妊娠・出産の希望などによって次のような治療が行われます。軽度な子宮内膜症であれば、子宮内膜の増殖を抑制するために低用量ピルや黄体ホルモンが用いられます。また、痛みに対しては一般的な鎮痛剤で対処します。チョコレート嚢胞など悪性が疑われる場合、また大きい場合、不妊症の原因と考えられる場合などでは病変部を切除する手術が行われます。また、将来的な妊娠の希望がない場合は、再発を予防するためにも病変部だけでなく子宮・卵巣・卵管なども同時に摘出することがあります。低侵襲な腹腔鏡下手術で行うことが可能です。子宮内膜症は明確な発症メカニズムが解明されていないため、現状では確立した予防法がありません。しかし、発症した場合は放置すると周辺組織との癒着が生じ、月経痛などがひどくなるだけでなく、不妊の原因になる可能性もあります。月経痛の悪化、経血量の増加などの症状がある場合は、できるだけ早く婦人科で検査を受けるようにしましょう。また、症状のない方も一度は検診を受けられることをおすすめします。
チョコレート膿腫
卵巣に生じる子宮内膜症のことです。子宮内膜症とは、本来であれば子宮の内部のみに存在する子宮内膜が子宮以外の部位に増殖する病気のことであり、チョコレート嚢胞は卵巣内で子宮内膜細胞が増殖します。子宮内膜は生理時に剥がれ落ちるため出血を生じますが、チョコレート嚢胞では卵巣内で生じた出血が排出されずにたまってチョコレートのような形状になることからこのような名前で呼ばれています。チョコレート嚢胞は20歳代や30歳代の若い世代が発症しやすく、発症すると強い生理痛、排便痛、性交痛などがみられるほか、不妊症の原因となることも知られています。また、卵巣がんのリスクが高くなるとの報告もあるため注意が必要です。基本的な治療はホルモン療法や嚢胞を摘出する手術ですが、手術は卵巣機能を低下させる可能性もあるため慎重な実施が望まれます。チョコレート嚢胞は卵巣内に子宮内膜細胞が増殖することによって引き起こされる病気です。子宮の内部以外で子宮内膜が増殖する原因としては、逆流した経血に含まれる子宮内膜の組織が子宮内以外の場所に付着するという“月経逆流説”が有力視されています。しかし、どのようなメカニズムで子宮内膜が卵巣内で増殖するのか明確には分かっていません。また、子宮以外の部位に増殖した子宮内膜細胞も生理の時に出血を生じるため、卵巣内には古くなった血液がどんどんたまっていきます。このようにたまった血液は茶色に変色してチョコレートのような形状になります。チョコレート嚢胞を発症すると卵巣の内部に古い血液がたまっていくため卵巣がどんどん大きくなっていきます。また、生理中は卵巣内で増殖した子宮内膜細胞からサイトカインなどの物質が分泌され、強い下腹部痛や腰痛などいわゆる“重い生理”のような症状が引き起こされます。さらに、進行すると生理中ではないとき、特に排卵期に下腹部痛や腰痛、排便痛、性交痛などの症状が現れるようになります。なお、チョコレート嚢胞は将来的な不妊につながることも多く、40歳以上では卵巣がんに移行する可能性が高くなるため注意が必要です。チョコレート嚢胞が疑われる場合は、次のような検査が行われます。卵巣の病変の有無を確認し、大きさなどを評価するために画像検査が必要です。もっとも簡便に行うことができるのは超音波検査ですが、チョコレート嚢胞では卵巣がんなどとの鑑別を行うためにCTやMRIなどによる検査が必要となります。チョコレート嚢胞を発症すると“CA-125”という腫瘍マーカーが上昇することがあるため、診断の手がかりの1つとして血液検査を行うのが一般的です。また、貧血の有無など全身状態を把握するために血液検査を行うこともあります。チョコレート嚢胞は嚢胞の大きさや症状などによって治療方法が大きく異なります。軽症で自覚症状もほとんどない場合は特別な治療をせずに定期的な経過観察のみをしたり、痛み止めなどを用いたりする対症療法を行います。一方、嚢胞が大きい場合や症状が強い場合は、嚢胞を縮小させる効果があるホルモン療法(低用量ピル療法ないし黄体ホルモン療法)が行われることがあります。また、卵巣や嚢胞を摘出する手術が行われることもありますが、術後に卵巣の機能が低下する可能性があるため妊娠を希望する人に対しては慎重な治療法の選択が行われます。チョコレート嚢胞の明確な発症メカニズムは解明されていないため、確実な予防法はないのが現状です。しかし、チョコレート嚢胞は放っておくと卵巣がんになる可能性もあるため、強い生理痛などの症状が続くときは軽く考えずに病院を受診しましょう。また、チョコレート嚢胞は術後の再発率が高いため、予防的ホルモン療法がすすめられます。治療後も定期的に検査を受けて再発の有無を確認することが大切です。
漢方と鍼灸
お血の漢方薬や食養生やサプリが何種類もあるのでその方の異常卵巣に合わせて最適な漢方やツボを選択します。癌の反応穴も確認しておきます。チョコレート膿腫の相談で来られた方は今のところすべて改善しております。
煎じ
・当帰芍薬散(当帰・川芎・芍薬・白朮・茯苓・沢瀉)『金匱要略』
浮腫みがあり、血行が悪く、冷え性な女性に用いられます。
・桂枝茯苓丸(桂枝・茯苓・牡丹皮・桃仁・芍薬)『金匱要略』
お血を減らしていきます。
・温経湯(呉茱萸・当帰・川芎・芍薬・人参・桂枝・阿膠・生姜・牡丹皮・甘草・半夏・麦門冬)『金匱要略』
・加味帰脾湯(人参・白朮・茯苓・黄耆・竜眼肉・酸棗仁・遠志・木香・甘草・当帰・生姜・大棗・柴胡・山梔子)『内科摘要』
・芎帰調血飲(当帰・川芎・白朮・茯苓・熟地黄・陳皮・烏薬・香附子・乾姜・益母草・牡丹皮・甘草・生姜・大棗)『万病回春』
・大黄牡丹皮湯(大黄・牡丹皮・桃仁・冬瓜子・芒硝)『金匱要略』
・桃核承気湯(桃仁・大黄・甘草・芒硝・桂枝)『傷寒論』
・柴胡疎肝湯(柴胡・橘皮・川芎・芍薬・枳殻・甘草・香附子・山梔子・生姜)『張氏医通』
・升陽燥湿湯(升麻・葛根・独活・姜活・芍薬・人参・炙甘草・柴胡・防風・甘草・大棗・生姜)『内外傷弁惑論』
・清玉散料(当帰・川芎・地黄・牡丹皮・陳皮・黄連・升麻・甘草・半夏・茯苓・芍薬・蒼朮・香附子・黄芩・柴胡・生姜)『寿世保元』
・調栄湯(当帰・川芎・地黄・芍薬・人参・甘草・茯苓・白朮・川骨・牛皮消)『華岡青洲』
・八味帯下方(山帰来・川芎・木通・金銀花・茯苓・大黄・当帰・陳皮)『名家方選』
・八珍湯(当帰・川芎・芍薬・熟地黄・人参・白朮・茯苓・甘草・生姜・大棗)『薛立齋』
・白葱散料(川芎・当帰・地黄・芍薬・4枳殻・厚朴・莪朮・三稜・茯苓・桂皮・乾姜・人参・川楝子・神麹・麦芽・青皮・茴香・木香・葱白・食塩少々)『医学入門』
・茯苓補心湯(当帰・川芎・芍薬・熟地黄・陳皮・半夏・茯苓・桔梗・枳殻・前胡・葛根・紫蘇葉・人参・木香・甘草・生姜・大棗)『医塁元戒』
・龍胆瀉肝湯(柴胡・沢瀉・車前子・木通・地黄・当帰・竜胆)『李東垣』
など(薬局製剤以外も含む)
習慣性流産
人工流産ではなく自然流産を連続3回以上繰り返すことを指します。自然流産を繰り返す場合、何かしらの原因となる病気が隠れていることもあります。そのため、原因に応じた治療介入が行われます。適切な治療を受けることで、正常な妊娠・出産につながることも十分期待できるため、流産を繰り返す際には医療機関を受診し、治療を受けることが推奨されます。習慣流産は、免疫学的な異常や子宮奇形、内分泌異常、染色体異常などを原因として発症します。免疫学的な異常ですと代表的な病気は、抗リン脂質抗体症候群です。抗リン脂質抗体症候群では、胎盤に微小な血栓が詰まり機能不全になることで胎児の血流不全が起こり、流産を繰り返す原因になることがあります。子宮の形が正常とは異なる子宮奇形も、習慣流産の原因のひとつです。子宮奇形があると、子宮内の空間が狭くなってしまい、胎児が発育するスペースが確保されないことがあります。その他に、甲状腺機能低下症、卵巣の機能低下、感染症、染色体レベルでの異常なども習慣流産の原因となることが知られています。習慣流産では、自然流産を連続して3回以上繰り返します。流産では、生理痛のようなお腹の張りや腹痛、出血などの症状が認められます。流産を繰り返すことから、なかなか挙児に至らない可能性があります。習慣流産では、原因によってはその他の症状が出現することもあります。抗リン脂質抗体症候群では血栓が形成されるリスクが高まりますが、脳梗塞の発症に至ることもあります。その他、甲状腺機能低下症であれば疲れやすさや全身のだるさ、便秘などの症状が現れます。また、感染症であれば膣分泌物の変化や腹痛、局所のかゆみなどを伴うことがあります。習慣流産では、内診や基礎体温測定などに加えて、原因検索を目的としたさまざまな検査が行われます。免疫異常の検索を目的とした自己抗体の検出や、甲状腺機能や感染症の有無などを評価するための血液検査が行われます。また、血液検査では、染色体検査やHLA型の検索なども行われます。その他、習慣流産は子宮の形態異常が原因となることもあるため、これを評価するための超音波検査、子宮卵管造影、MRI検査なども行われます。習慣流産では原因に応じた治療介入が行われます。抗リン脂質抗体症候群が原因の場合には、アスピリンやヘパリンなどを用いることで流産の予防を図ります。
また、甲状腺機能の低下が原因の場合には甲状腺ホルモンの補充療法が行われますし、感染症が原因の場合には病原体に応じた治療薬が使用されます。子宮の形態異常が原因と考えられる際には、手術が検討されます。
漢方と鍼灸
各症状、疾患によって最適な漢方、食養生やサプリ、ツボを選択します。自己免疫の反応穴、感染症の反応穴、内分泌の反応穴からも参考にします。
煎じ
・当帰芍薬散(当帰・川芎・芍薬・白朮・茯苓・沢瀉)『金匱要略』
妊娠中の腹痛や月経痛に良く使われます。
・当帰散(当帰・芍薬・黄芩・川芎・白朮)『金匱要略』
当帰は月経を調整し、子宮の痙攣を緩めて、鎮痛の効果があります。川芎にも当帰と同じように血行を良くし、月経異常に効果があります。芍薬は平滑筋の緊張を緩め、黄芩には安胎作用があると考えられていました。
・芎帰膠艾湯(川芎・阿膠・甘草・艾葉・当帰・芍薬・地黄)『金匱要略』
・芎帰膠艾湯(艾葉・阿膠・川芎・当帰・甘草)『備急千金要方』
・芎帰補中湯(川芎・五味子・阿膠・黄耆・当帰・芍薬・白朮・人参・杜仲・甘草・艾葉)『奇効良方』
など(薬局製剤以外も含む)
妊娠悪阻
いわゆる“つわり”が重症化し、頻回な嘔吐と著しい食思不振が生じることで脱水や栄養代謝障害を生じる病気のことです。“つわり”は、妊娠による急激なホルモンバランスの変化などが引き金となって、妊娠5~8週目頃に現れることが多い症状です。妊婦の半数以上は“つわり”を経験するとされていますが、妊娠12~16週頃には自然と改善していくことが多いため、治療が必要になることはほとんどありません。一方、重度な“つわり”である妊娠悪阻は妊婦の約0.5%に発症し、適切な治療を受けないと脳や肝臓に障害を引き起こすなど重篤な合併症を生じることも少なくありません。妊娠悪阻は妊婦の半数以上が経験するとされる“つわり”が重症化したものです。どのようなメカニズムで“つわり”が引き起こされるのかは明確には解明されていませんが、妊娠に伴って女性ホルモンの一種であるエストロゲンや、着床することで分泌されるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)と呼ばれるホルモンの分泌量が急激に上昇することが原因のひとつと考えられています。また、“つわり”が重症化して妊娠悪阻を引き起こす原因もはっきりと分かっていませんが、初めての妊娠や多胎妊娠、母体の肥満、摂食障害の既往などが発症のリスク要因と考えられています。また、妊娠・分娩への不安や心理的葛藤などの精神的因子の関与に加えて、母親や姉妹などの近い親族が妊娠悪阻になったことがある場合、自身も発症する可能性が高いと報告されていることから、遺伝要因も示唆されているのが現状です。妊娠悪阻は妊娠5~8週頃に頻回な吐き気や嘔吐が生じることで体内から水分や電解質が失われ、体を維持するために必要なエネルギーや栄養素を補うことができなくなる病気です。重症化すると体内のさまざまなバランスが乱れ、命に関わることも珍しくありません。さらに、脱水や長期臥床が深部静脈血栓発症のリスク因子となります。妊娠悪阻は重症度によって三つの段階に分けられますが、それぞれの段階で現れる症状は次のとおりです。第1期は吐き気や嘔吐が1日を通して頻回に生じ、食事や水分を取ることが困難になります。体重は減少を続け、脱水や栄養不足に伴い、めまいやだるさ、頭痛などの症状が現れることも少なくありません。このため、外出どころか日常的な家事などもできなくなるケースがあります。第2期は頻回な嘔吐や、極端な摂食量の不足が続くことで、極度な脱水状態に陥ります。尿量は減少し、皮膚の乾燥や口が渇くなどの症状が現れ始め、血圧の低下や頻脈、発熱などが生じるようになります。第3期はさらに脱水や栄養不足が進行すると、肝臓や脳に重篤なダメージが加わります。特にビタミンB1が不足することによって発症する“ウェルニッケ脳症”は妊娠悪阻の重篤な合併症のひとつで、記憶や運動機能に異常が生じます。そして半数以上の方に過去のことを思い出せない、新しいことを覚えられない、作り話をするといった特徴的な症状が現れる“コルサコフ症候群”と呼ばれる後遺症を残すとされています。また、万が一治療が遅れたり、治療がうまくいかなかったりした場合は、胎児死亡や多臓器不全による母体死亡に至るケースもあります。妊娠悪阻は頻回な嘔吐と極端な摂食量の減少があり、体重が妊娠前より5%以上減少している場合に発症が疑われます。妊娠悪阻の明確な診断基準は定められていませんが、次のような検査を行って診断を下します。妊娠悪阻の可能性を簡易的に調べる検査として広く行われるのが、尿検査による“ケトン体”の検出です。ケトン体とは、飢餓状態に陥ったときに体内に蓄えられた脂肪が、エネルギーとして分解される過程で産生される物質であり、通常は尿中に検出されることはありません。しかし、妊娠悪阻によって飢餓状態に陥ると、尿中に検出されるようになるため、妊娠悪阻発症の有無を調べるために有用な検査となります。検査は採取した尿に専用の試験紙を浸すだけで行うことができるため、妊婦検診などでも広く行われています。尿検査でケトン体が検出されると妊娠悪阻と診断されますが、一般的には体内の電解質の状態や脱水の有無、肝臓や腎臓の機能を調べるために血液検査が行われます。つわりに対しては、心身の安静と休養、少量頻回の食事摂取、水分補給を促し重症化を防ぎます。妊娠悪阻を根本的に治す治療法はなく、失われた水分や電解質を補い、吐き気が強い場合は、適宜制吐剤(吐き気止め)などを使用する対症療法が行われます。口から水分などが摂取できるケースでは、電解質が含まれた経口補水液を摂取するのが望ましいですが、妊娠悪阻では経口摂取が困難なケースがほとんどです。このため、入院したうえで、いったん絶食し、体内に必要な電解質やビタミンB1が含まれる輸液治療が行われます。これらの治療を続けることで、多くは妊娠16週頃には症状が改善していきます。一方で、長期間症状が治まらない場合や体重減少が著しい場合などは、通常の点滴ではなく、首や鎖骨の下にある太い血管の中に管を入れてカロリーや栄養素がより多く入っている輸液(中心静脈栄養)を行うことも少なくありません。また、まれではありますがこれらの治療を行っても症状が改善せず、第3期の症状が現れるような場合には、ウェルニッケ脳症の発症を防ぐために人工中絶手術が選択されることもあります。
漢方と鍼灸
つわりを悪化させないようにすることが大切です。経口摂取が出来なくなった場合では輸液治療になりますので漢方や食養生は飲めません。当院ではつわりを改善しながら気持ちを落ち着かせる漢方を使い、食養生を少しずつ摂取して頂きミネラル不足を改善します。つわりのご相談で良くならなかった方はいません。ご相談ください。
煎じ
・小半夏加茯苓湯(半夏・生姜・茯苓)『金匱要略』
半夏・生姜は悪心・嘔吐を治します。
・半夏厚朴湯(半夏・生姜・茯苓・厚朴・紫蘇葉)『金匱要略』
小半夏加茯苓湯に厚朴と紫蘇葉を加えたものです。
・安中散(甘草・延胡索・良姜・茴香・桂皮・牡蛎・縮砂)『太平恵民和剤局方』
・乾姜人参半夏丸(乾姜・人参・半夏)『金匱要略』
・呉茱萸湯(呉茱萸・人参・大棗・生姜)『傷寒論』
・五苓散(猪苓・沢瀉・白朮・茯苓・桂枝)『傷寒論』
・生姜瀉心湯(生姜・黄連・黄芩・人参・甘草・大棗・半夏・乾姜)『傷寒論』
・参蘇飲(陳皮・枳殻・桔梗・甘草・木香・半夏・紫蘇葉・葛根・前胡・人参・茯苓・生姜・大棗)『太平恵民和剤局方』
・二陳湯(半夏・陳皮・茯苓・甘草・生姜)『太平恵民和剤局方』
・半夏瀉心湯(半夏・黄連・黄芩・人参・乾姜・甘草・大棗)『傷寒論』
・橘皮湯(橘皮・生姜)『金匱要略』
・紫蘇和気飲(大腹皮・人参・川芎・陳皮・芍薬・紫蘇葉・当帰・甘草)『普済本事方』
・紫蘇和気飲(紫蘇葉・当帰・川芎・芍薬・陳皮・大腹皮・香附子・甘草・生姜・葱白・人参)『済世全書』
・小半夏湯(半夏・生姜)『金匱要略』
・伏竜肝煎(黄土・半夏・生姜・茯苓)『原南陽』
・養胃湯(当帰・芍薬・白朮・茯苓・陳皮・藿香・縮砂・神麹・半夏・香附子・甘草・生姜・大棗)『寿世保元』
・理中湯(人参・乾姜・甘草・白朮)『傷寒論』
など(薬局製剤以外も含む)
冷え症
手足の先端、腰など体の一部が冷えやすくなる状態のことを指します。医学的な病名ではなく、身体症状の1つです。私たちの体には体温を調節する仕組みが備わっており、寒さを感じると血管が収縮することで体内の熱を外に逃がしにくくしたり、震えによる筋肉の運動で熱が産生されたりすることで皮膚の温度を保っています。しかし、この調節が上手くいかなくなると、手足の先端などが冷えやすくなるのです。原因は多岐にわたりますが、一般的には男性よりも女性のほうが冷え症になりやすいとされています。冷え症が続いているからといって健康に大きなダメージを与えることはありません。しかし、適切な対処を講じずに放置すると頭痛、肩こり、しびれ、便秘・下痢などの身体的症状、イライラ感や不眠など精神的症状を引き起こすことがあります。また、低血圧や貧血、甲状腺機能低下症などの病気が背景にあるケースも少なくないため注意が必要です。冷え症は上述したように、体温調節の仕組みが上手く働かなくなることによって引き起こされる症状です。その原因は多岐にわたりますが、単純に薄着や過度な冷房などが原因となるほか、以下のようなものも原因として挙げられます。血管の収縮などの体温調節は自律神経によって司られています。そのため、ストレスや過度な疲れ、環境の変化、女性ホルモンの乱れなどによって自律神経の働きが乱れると、体温調節もうまく働かなくなり冷え症を引き起こすことがあります。特に夏の空調などで外気と室温の差が激しい環境になると自律神経の働きが乱れやすくなり、暑い時期に冷え症になるケースも少なくありません。貧血や低血圧などの病気、運動不足や喫煙習慣、締め付けの大きな服装など、血流が低下しがちな原因があると特に手足の先などに体内の熱が届きにくくなるため、冷え症になりやすくなります。筋肉は熱を産生する器官でもあるため、筋肉量が少ないと体内で熱が作られにくくなり冷え症になることがあります。冷え症は甲状腺機能低下症、レイノー病、全身性強皮症などの自己免疫疾患、閉塞性動脈硬化症などの症状の1つとして現れることがあります。対策を講じても冷え症が改善しないときは、背景に何らかの病気が隠れていることもあるので注意が必要です。冷え症はその名のとおり、皮膚の温度が低下する症状のことです。発症する部位や時期などはさまざまであり、よく見られるのは寒い季節や過度な冷房などに晒された際に手足の先端に発症するタイプです。重症な場合には手足の先端がいわゆる“しもやけ”になったり、皮膚の色が白くなりしびれや痛みを引き起こしたりするケースも少なくありません。一方で、下半身の筋力が低下しているケースでは脚や腰を中心に冷えやすくなり、冷たい飲食物を多量に摂取すると胃や腸などの消化器官が冷えることもあります。また、冷え症は病気ではなく“体質”の1つと捉えられることもありますが、冷えが長く続くと頭痛、肩こり、腰痛、関節の痛みやしびれ、便秘や下痢などの身体的症状、イライラ感や不眠などの精神的症状を引き起こすため軽く考えずに適切な対処が必要です。通常、冷え症に対して医学的な検査を必要とすることは多くはないかもしれません。しかし、適切な対処を講じても冷え症が改善しない場合は、何らかの病気が原因の可能性があります。病気が疑われる場合は、貧血や甲状腺機能低下症、自己抗体(自分の体を攻撃するタンパク質)の有無を調べるための血液検査、血管の閉塞や狭窄を調べるための画像検査などが必要に応じて行われます。何らかの病気が原因で冷え症になっている場合は、原因となる病気の治療が優先して行われます。また、冷え症の治療は必要ないとされることがありますが、冷えそのものや伴ってみられる諸症状に対して漢方薬による治療を行うこともあります。冷え症は生活習慣に起因するケースが多いため、次のような対策を講じることが大切です。睡眠リズムなどが乱れた不規則な生活は冷え症の原因となる自律神経の乱れを引き起こします。日ごろから規則正しい生活を心がけ、ストレスを溜め過ぎないよう心がけましょう。締め付けの多い衣類や靴は血行を悪化させるので、できるだけゆったりしたものを着用することが大切です。また、寒い季節や冷房が強いときは体を冷やしすぎないように衣類で調節するようにしましょう。特に脚の筋肉量が低下すると下半身の冷えを引き起こしやすくなるため、適度な運動を行い、筋力量を増やすことも大切です。胃腸を冷やすと全身の冷えにつながります。飲み物はなるべく常温以上のものを飲むようにし、食べ物も冷えたものは避けて温かいものを取るようにしましょう。
漢方と鍼灸
冷えの強い箇所からどの漢方、食養生やサプリ、ツボが最適かわかります。また養生も大切です。お米、味噌汁を基本とし冷たい物・冷やす物を極力控える、または食べたら暖かい物も摂る。低体温も免疫、自律神経が乱れます。寝る前は暖かい物を飲んで寝ると熟睡しやすいですよ。
「冷えは万病の元」です。冷えすぎて自分が冷えているかわからない方がいらっしゃいます。
問診の仕方を工夫しましょう。不妊症の原因にもなりますので周期表をご持参くださればすぐわかります。
煎じ
・当帰四逆加呉茱萸生姜湯(当帰・芍薬・桂枝・細辛・木通・甘草・大棗・呉茱萸・生姜)『傷寒論』
手足の血行を良くし、手足を温める方剤です。川芎・当帰・桂枝は手足の末梢の血行を良くします。呉茱萸・生姜は胃を温めます。
・当帰芍薬散(当帰・川芎・芍薬・白朮・茯苓・沢瀉)『金匱要略』
下半身にむくみがあり、血行の悪い冷え性の方に良いです。
・苓姜朮甘湯(茯苓・白朮・乾姜・甘草)『金匱要略』
白朮・茯苓に利尿作用があり、乾姜がお腹や腰を温める作用があります。
・麻黄附子細辛湯(麻黄・細辛・附子)『傷寒論』
・十補湯(人参・白朮・茯苓・黄耆・桂枝・当帰・川芎・熟地黄・甘草・芍薬・附子・乾姜・大棗)『済世全書』
・升麻附子湯(升麻・葛根・白芷・黄耆・附子・人参・草豆寇・益智・甘草・葱白)『万病回春』
・升陽燥湿湯(黄芩・橘皮・防風・良姜・乾姜・郁李仁・甘草・柴胡・白葵花)『蘭室秘蔵』
・腎著湯(茯苓・白朮・乾姜・甘草・杏仁)『三因極一病証方論』
・白朮散(白朮・川芎・蜀椒・牡蛎)『金匱要略』
など(薬局製剤以外も含む)
腟炎
子宮頸部と外陰をつなぐ腟の粘膜に炎症が起こることをいいます。特に成人女性に多くみられますが、子どもから高齢の人まで、どの年代の人でも起こり得る病気です。腟の表面は女性ホルモン(卵胞ホルモン)によって粘膜で覆われており、腟内にはデーデルライン桿菌と呼ばれる乳酸菌が常在しています。デーデルライン桿菌は腟内を酸性に保ち、腟内の細菌感染を防ぐはたらき(自浄作用)があります。しかし、何らかの理由で自浄作用が追いつかないほど細菌が増殖するなど、腟内の菌のバランスが崩れると炎症を引き起こします。また、腟炎の原因になる菌の中にはまれに子宮にも広がるものがあり、子宮内膜炎などを引き起こす可能性があります。腟炎には複数の種類があります。カンジダと呼ばれる真菌が増殖することによって炎症が生じた状態を指します。カンジダは日頃から体の中にある、いわゆる常在菌の1つです。主に病気や疲れ、妊娠などで体の抵抗力が落ちている場合や、かぜなどで抗菌薬を内服してデーデルライン桿菌が死滅し腟内の自浄作用が落ちた場合、真菌が過剰に増殖して炎症を引き起こすと考えられます。また、カンジダに感染しているパートナーとの性交をきっかけに感染することもあります。大腸菌やブドウ球菌、溶連菌といった細菌によって生じる炎症で細菌性腟炎は何らかの理由で腟内の自浄作用が弱まっているときや、下痢などで陰部を清潔に保つことが難しいときなどに原因菌が腟内で感染を引き起こし、発症すると考えられています。そのほか、タンポンの出し忘れで腟内に細菌が増殖して発症することもあります。トリコモナスと呼ばれる原虫が腟に寄生することによって炎症が起きた状態です。トリコモナス腟炎はパートナーが感染者で性交によって感染する場合と、公衆浴場やトイレなどで感染する場合があります。老人性膣炎は閉経後、女性ホルモンがほとんど分泌されなくなります。それによって腟内の粘膜が萎縮し、腟内の自浄作用がなくなり、炎症が生じます。閉経により女性ホルモン“エストロゲン”の分泌が低下することによって起こります。腟炎の症状は病気によって多少異なりますが、特におりものの量や色、臭いの異常が多くみられます。おりものが多いと陰部が蒸れ、かゆみや痛みを続発することもあります。また、妊娠中に細菌性腟炎が生じると、流産や早産、胎児が感染症を発症する原因となることもあるため、速やかに治療を開始することが大切です。
カンジダ腟炎は腟内のかゆみと、カッテージチーズのような白いおりものが生じます。カンジダが腟内から外陰部まで広がると、外陰部にかゆみが出ることもあります。細菌性腟炎は腟内が赤く腫れ、黄色や茶褐色、黄緑色などのおりものがみられることがあります。おりものに悪臭を伴うこともあります。トリコモナス腟炎は腟内から外陰部にかけて、かゆみや灼熱感が生じ、排尿や性交の際にも痛みが生じる可能性があります。そのほか、悪臭があり黄色っぽいおりものが生じることもあります。老人性腟炎は腟の乾燥・萎縮により、腟内の灼熱感、しみるような痛みや違和感を覚えることがあります。また、性交時に痛みや出血が生じやすくなります。腟炎が疑われる場合、まずは問診・内診を行います。感染による炎症と考えられる場合は腟内にあるおりものを専用の綿棒で採取し、培養検査を行います。おりものの採取に痛みはありません。培養により原因となる真菌・細菌・原虫などを特定できれば、それに合わせた治療を行います。腟炎では原因に応じた薬物療法を検討することが一般的です。腟内の洗浄を行い、腟錠を投与します。症状は数日で落ち着いてくることが多いですが、悪化や再発を防ぐためにも途中で治療を中断せず、医師の指導どおりに治療を継続することが大切です。性行為が原因と考えられる場合は、パートナーに相談し治療を受けてもらうとよいでしょう。カンジダ腟炎同様、腟内の洗浄や腟錠の投与が検討されるほか、抗菌薬の処方も検討されます。トリコモナス腟炎は飲み薬や腟錠を用いて治療を行います。性行為が原因と考えらえる場合は、パートナーにも同時期に治療を受けてもらうことが重要です。
老人性腟炎は女性ホルモンの減少により生じるため、ホルモンを補充する飲み薬や腟錠が処方されることが一般的です。また、細菌による炎症が生じている場合は抗菌薬の腟錠を処方することも検討されます。腟炎にはさまざまな種類がありますが、基本的に外陰部を清潔に保つことが予防につながります。下着や洋服などによる蒸れや擦れを防ぎ、通気性のよい状態を保つほか、排便後などは陰部をよく洗って汚れが残らないようにしましょう。感染症にかかりにくい体を作るために、規則正しい生活を送り抵抗力を高めることも大切です。
また腟炎の中には性交によって感染するものもあります。そのため、性交の際はコンドームを使用して感染を予防するほか、気になる症状があるときは性交を控え、速やかに医療機関を受診しましょう。再発を繰り返す場合には、パートナーにも医療機関の受診を促すとよいでしょう。
漢方と鍼灸
抗生物質、抗真菌が合わない方は、効果を高めたい方はご相談ください。また抵抗力をつけるご相談も受け付けています。老人性の場合、女性ホルモン補充療法を希望しない場合は、漢方と食養生やサプリがございます。
煎じ
・竜胆瀉肝湯(黄連・黄芩・黄柏・山梔子・当帰・川芎・芍薬・地黄・連翹・薄荷・木通・防風・車前子・竜胆・沢瀉・甘草)『一貫堂』
慢性の炎症性疾患に使われます。
・加減六合湯(椿根・芍薬・当帰・川芎・熟地黄・陳皮・茯苓・甘草・半夏・貝母・白朮・黄柏・知母・生姜)『万病回春』
・升陽燥湿湯(黄芩・橘皮・防風・良姜・乾姜・郁李仁・甘草・柴胡・白葵花)『蘭室秘蔵』
・清玉散料(当帰・川芎・地黄・牡丹皮・陳皮・黄連・升麻・甘草・半夏・茯苓・芍薬・蒼朮・香附子・黄芩・柴胡・生姜)『寿世保元』
・治帯下方(牡蛎・山梔子・芍薬・甘草)『名家方選』
・調栄湯(当帰・川芎・地黄・芍薬・人参・甘草・茯苓・白朮・川骨・牛皮消)『華岡青洲』
・八味帯下方(山帰来・川芎・木通・金銀花・茯苓・大黄・当帰・陳皮)『名家方選』
・附桂湯(附子・桂皮・黄柏・知母・升麻・甘草・黄耆・人参)『医学入門』
など(薬局製剤以外も含む)
2月のお休みと、祝日の営業時間
[お休み]
2月4日(日)・5日(月)
2月11日(日)・12日(月)
2月18日(日)・19日(月)
2月25日(日)・26日(月)
【祝日】
2月23日(金)
※営業時間:10時から16時まで
ご予約: 03-3300-0455 までお電話ください。
どうか皆様も、温かいお部屋でリラックスしてお過ごしください。
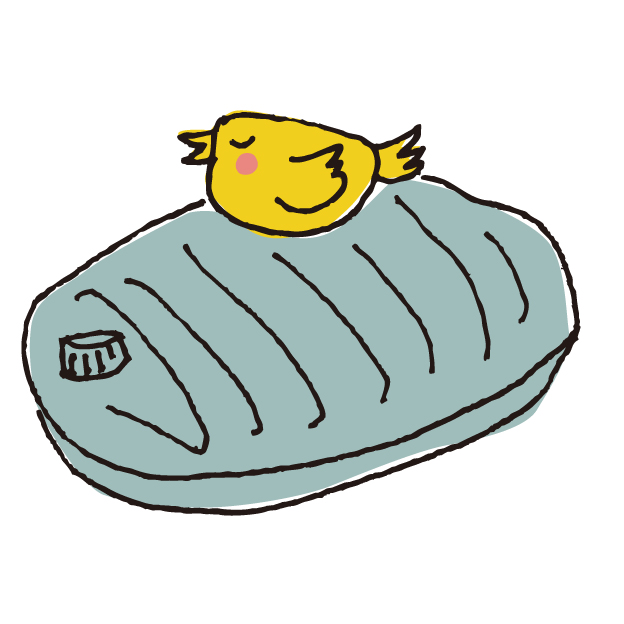
【筋骨格系】の症状でお悩みの方に
「もしも、親や身近な人、あるいは自分自身が【筋骨格系】の病気になったらどうしよう…」そんな不安を抱いたことはありませんか。
身近な症状として腰痛、ぎっくり腰(急性腰痛)などの増加が問題となっています。年を重ねることで、骨粗鬆症、坐骨神経症などの方が増えています。成人・高齢化社会においても、筋骨格系の健康は非常に重要です。
当院の【筋骨格系】の病気へのこだわりは漢方薬の選薬、鍼灸の施術と食養生を大切にしていることです。どこに行っても良くならなかった方の最後の砦になりたい、そんな気持ちでアドバイスさせていただきます。

腰痛、ぎっくり腰(急性腰痛)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症・広範脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症・黄色靱帯骨化症、四十肩・五十肩・六十肩(肩関節周囲炎)、変形性膝関節症、むち打ち(外傷性頚部症候群)、打撲・骨折と予後神経痛、腱鞘炎・ドケルバン病・ばね指、骨粗鬆症、骨髄炎・化膿性骨髄炎、骨端症・ケーラー病・シーバー病、手の痺れ・足の痺れ、足の痛み・かかとの痛み、筋肉痛・筋肉疲労・線維筋痛症、変形性股関節痛・特発性大腿骨頭壊死症、脊椎すべり症、脊椎分離症、坐骨神経症、肩こり、変形性肩関節症、肋間神経痛、手根管症候群、こむら返り、頚椎症性神経根症・頚椎症性脊髄症、バレリュー症候群、ヘパーデン結節・プシャール結節
自分自身や家族・同僚、友人など周りの人について「筋骨格系」と思われる症状に気づいたら一人で悩まず、不二薬局にご相談ください。
■漢方の不二薬局、はりきゅう治療院 藤巻一心堂へのアクセスはこちら
■遠方の方は、オンライン(電話)でご相談いただけます。